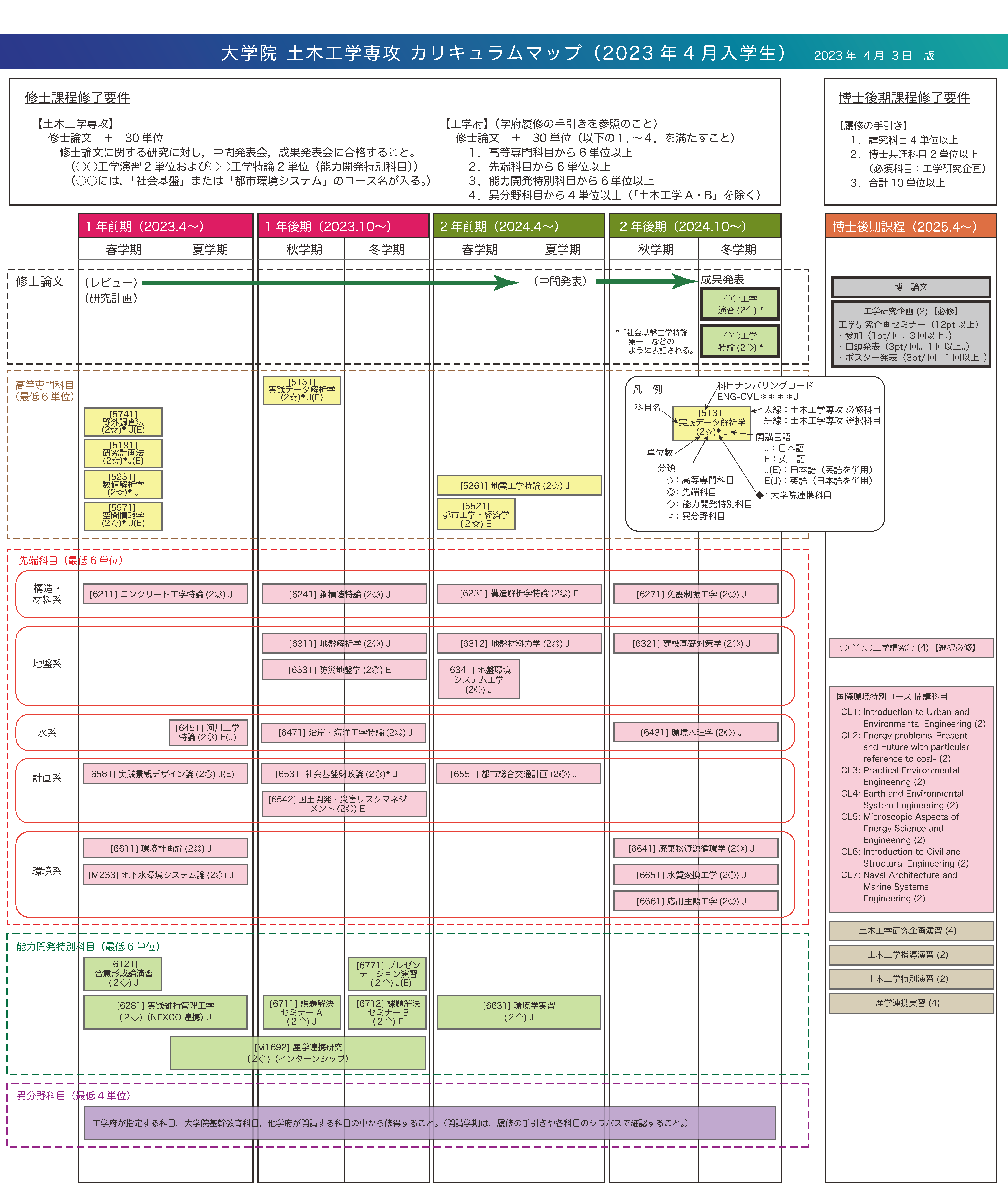土木工学専攻の概要
社会基盤施設の設計・建設・維持管理や、地球規模から地域や都市レベルまでの環境問題や自然災害の分野に関する高度な専門知識と技術を,最先端の研究活動を通じて教育し,安全・安心で持続性のある社会を実現するための創造性豊かで柔軟な発想力を有する研究者・技術者を育成します。
教育目標
土木工学は、安全・安心で豊かな暮らしを持続的に営むための国土の基盤を整備・保全することを目的とした幅広い学問分野です.頻発する自然災害に対する防災技術、人工的な都市と自然や生態系との調和を目指す環境技術,高度な情報技術を活用した次世代型の交通システム、社会基盤施設の長寿命化技術の開発なども土木工学の学問分野です。
土木工学専攻では、安全・安心な社会や、豊かな自然を保全し、持続性のある社会環境を実現するため、高度専門知識を集積した技術力と柔軟な研究能力を備え、社会の指導的地位で活躍できる素養を有する研究者・技術者を組織的に養成するために、以下を教育目標としています。
修士課程
- 社会基盤施設の設計・建設・維持管理や、地球規模から地域や都市レベルまでの環境問題や自然災害の分野に関する基礎知識および十分な専門的知識を身に付けること。
- 責任感・倫理観を持ち、我が国の安全・安心な社会の構築に向けて、リーダーシップを発揮できる人材になり得ること。
博士課程
- 社会基盤施設の設計・建設・維持管理や、地球規模から地域や都市レベルまでの環境問題や自然災害の分野に関する基礎知識および十分な専門的知識を身に付け、国際社会において競争力のある人材になり得ること。
- 責任感・倫理観と自身の卓越した知識と技術に基づき、人類社会の安全・安心な社会や、自然環境と人間環境の調和した社会の構築に向けて、リーダーシップを発揮できる人材になり得ること。
カリキュラムの特徴
社会がCivil Engineeringに求める人材は,高度な専門家からジェネラリストまで実に多様です。建設都市系専攻では,数学や科学に基づく基礎知識,土木工学(構造・材料・地盤・水・計画・環境など)および周辺分野に関する専門知識を習得するとともに,それらを横断的に総合するために必要となるコミュニケーション能力,リーダーシップ力,課題解決力が身につけられるようにします。
カリキュラムマップ
土木工学専攻の科目が一覧で分かるように独自に作成したもの。
なお,学位プログラムの学修目標と各科目との関係を示した「カリキュラム・マップ」は,下記のリンク参照。
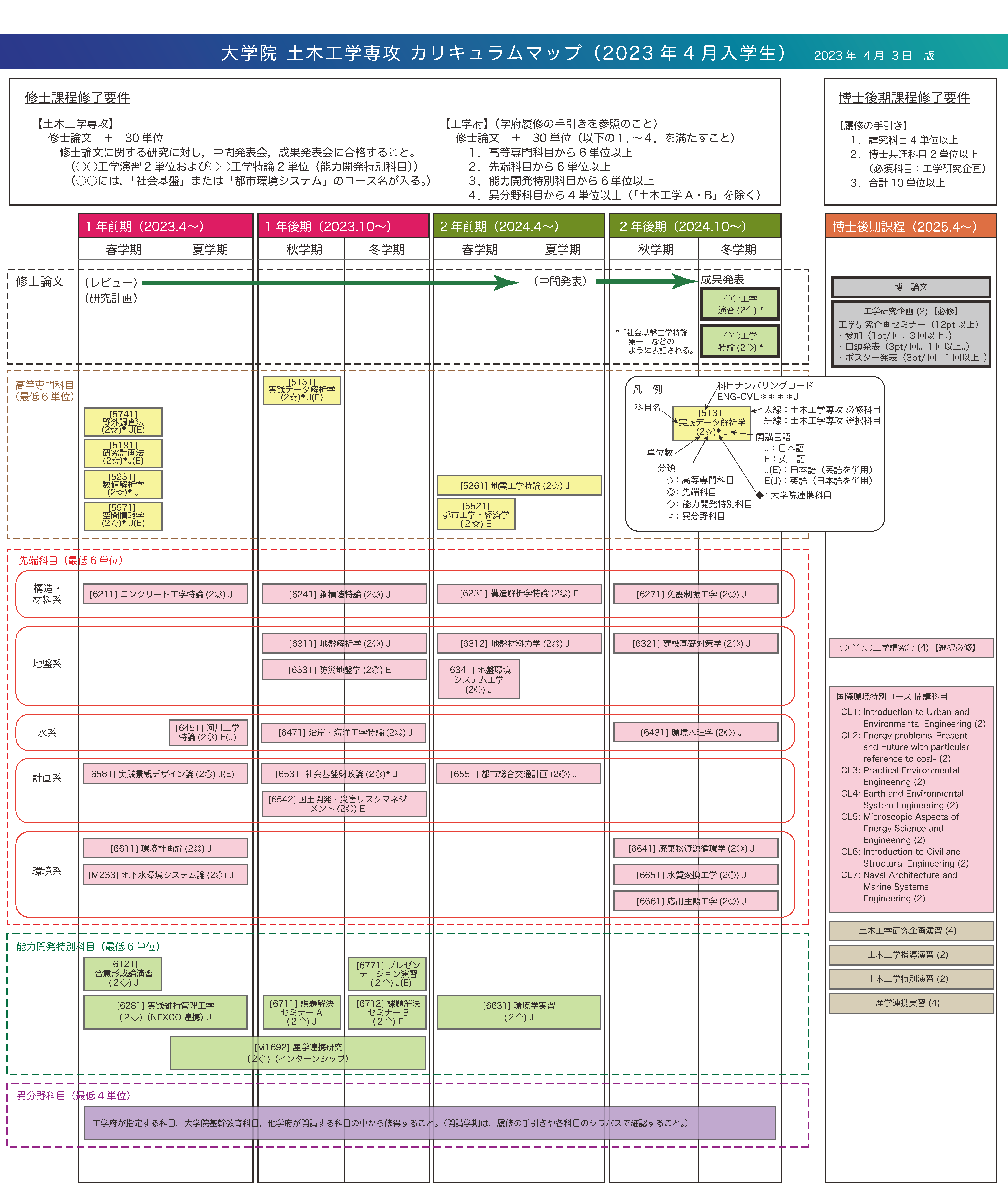
土木工学専攻における研究内容
社会基盤工学コース
| 構造解析学 |
- 自然災害(落石・土石流・竜巻)に対する防護構造に関する研究
- 打音・赤外線サーモ等を用いた構造物の健全度評価に関する研究
- 構造物の耐爆・耐火性能に関する研究
- 沿岸構造物の設計へ向けた流体・構造連成シミュレータの開発
- 数値解析に基づいた動く自然災害ハザードマップの構築
|
| 地震工学 |
- 社会基盤施設の耐震性向上のためのAI活用に関する研究
- 活断層を考慮した場合の高速道路網の耐震性向上に関する研究
- 河川をまたぐ橋梁の地震時安全性に関する研究
- 大地震時における変位制限装置の要求性能に関する研究
- 実験およびFEM解析に基づくゴム支承の限界状態特性の解明に関する研究
|
| 建設設計工学 |
- 化学・物質化学・電気化学に基づく被覆鋼材の連成劣化機構の解明
- 橋梁等の鋼構造物のミクロ腐食環境評価に基づくメンテナンス手法の提案
- 鋼構造物の致命的損傷予知シミュレータの開発
- 重度に劣化した鋼構造物に対する蘇生技術の開発
- 革新的電気化学腐食センサの開発と全産業分野への展開
|
| 建設材料システム工学 |
- 副産物系材料を用いた環境負荷低減型の建設材料の開発
- コンクリート構造物の診断のための非破壊・微破壊検査手法
- 電気化学的手法によるRC構造物の腐食抑制に関する研究
- 建設材料としての海水の利用に関する研究
- コンクリート構造物のASRの劣化機構・抑制対策に関する研究
|
| 地盤工学 |
- 地盤材料の力学と飽和・不飽和地盤の健全性評価
- 土地の高度利用のための地盤安定化に関する研究
- 新しい地盤材料の開発とその有効利用に関する研究
- 自然と調和した地盤環境保全技術の開発
- 土工の効率化と地盤内を調査・分析する技術の高度化
|
| 防災地盤工学 |
- 地盤の液状化対策と液状化リスク分析に関する研究
- 地盤災害および防災対策に関する数値解析手法の開発
- 防災システム・災害リスクマネージメントに関する研究
- 海洋波浪・津波による沿岸構造物の防災性能評価に関する研究
- 浚渫土砂を活用した超大型防災ブロックの開発
|
| グローバル地盤災害 |
- 産業廃棄物の有効利用に関する研究
- 自然災害(地震,津波,豪雨など)に強い地盤材料の開発と新技術
- 建設基礎を改良・補強する技術
- 地盤調査とモニタリングに関する技術
- 斜面災害対策法に関する研究
|
| 地圏環境工学 |
- GIS(地理情報システム)を用いた防災・環境分野への応用研究
- 地域防災に関する研究
- 自治体などの空間情報基盤の整備に関する研究
- 高速道路の維持管理に関する研究
- 炭酸ガスの地中貯留に関する研究
- 土砂災害および河川への土砂流出に関する研究
- グリーンインフラを活用した都市の評価に関する研究
|
都市環境システム工学専攻
| 国土政策・防災 |
- 人口動態,地域構造変化を考慮した防災対策に関する研究
- 建設マネージメント,社会資本マネージメントに関する研究
- 都市発展,都市財政,社会資本の関係に関する研究
- 社会資本整備,都市整備の国際協力に関する研究
|
| 交通システム工学 |
- 離島・過疎地の交通と生活圏の構成に関する研究
- 高齢社会を考えた交通とまちづくりに関する研究
- 非動力交通(自転車,歩行)及びバリアフリーに関する研究
- 長距離交通と都市計画に関する研究
- 交通テクノロジーの評価とその運用に関する研究
|
| 都市工学 |
- 将来技術の開発導入を含めた都市計画と交通工学
- 都市や世界が持続可能になるための制度設計の研究
- 資金メカニズムと技術戦略に関する研究
- 環境,資源,エネルギー,災害の経済・社会の研究
|
| 流域システム工学 |
- グリーンインフラ計画と導入
- 多自然川づくりと地域創生
- 水害,Eco-DRR(生態的災害リスク軽減手法)
- 流出抑制技術と水循環の再生
- 小水力発電導入
- 都市域における浸水被害予測と危機管理に関する研究
- 総合土砂管理に関する研究
|
| 都市環境工学 |
- 流域における総合的水管理と点源・面源汚濁負荷対策
- 下水の高度処理とリン資源・エネルギー回収,再生水の利活用
- 応用生態工学手法を用いた水質と底質の改善
- 竹炭・木炭および汚泥溶融スラグの賦活化とセシウムの吸着除去能力の改善
- アオコの発生抑制手法の開発
|
| 環境制御工学 |
- 持続型社会構築のための資源循環技術の開発
- 廃棄物の適正な埋立処分技術開発
- 廃棄物の循環資源化と有効利用のライフサイクル環境経済評価
- 災害廃棄物及び放射能汚染廃棄物の適正処理
- リモートセンシングによる環境・廃棄物管理
- アジア途上国における環境調査と対策研究
|
| 水圏環境工学 |
- 地域水循環機構の解明とその健全化に向けた提案
- 地下環境における物質輸送解析
- 表流水と地下水の交流解析
- 溶存シリカが凝集効果に及ぼす影響評価
- 豪雨場の診断と降雨予測モデルの開発
- 人工降雨に関する研究
- 古文書資料による土石流災害の抽出とその啓発に関する提言
|
| 生態工学 |
- 海岸・沿岸・海洋・河川の生態工学
- 生態系を活かした防災(Eco-DRR),グリーン・インフラ
- 生物生息地,生物多様性の保全・再生・管理
- 島の海洋保護区の設計や管理,漂流漂着ゴミ問題解決のための地域知と科学知の融合
- 水の持続可能な利用に関する地域~国内の環境計測,環境計画・政策,国際的枠組形成への参加
- 市民参加,科学技術コミュニケーション,人材育成
|
| 環境流体力学 |
- 沿岸域における流れ構造と物質輸送に関する研究
- 沿岸域における微量水銀動態の解明
- 沿岸域における温室効果ガスの動態に関する研究
- 地球温暖化が沿岸域に与える影響評価
- 流域の流木リスク評価に関する研究
- 流域圏における気候変動適応策に関する研究
|
| 沿岸海洋工学 |
- 高精度高潮波浪シミュレーションモデルの開発
- 沿岸災害における地球温暖化の影響予測
- 波浪観測・解析法の高度化に関する研究
- 関門航路の航路埋没に関する研究
- 越波に伴う飛沫・飛来塩分の発生と拡散過程に関する研究
|
各種資料へのリンク